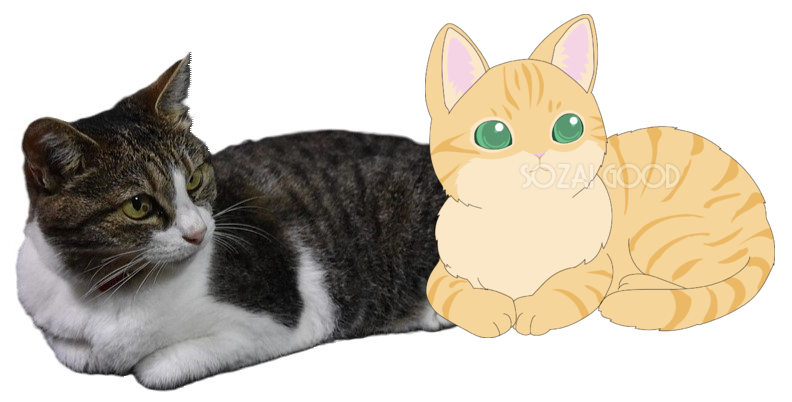かわち野第十集
ミケとノンノ
井上 文子
我家で飼った一代目の猫の名前は「ミケ」である。
私が四十代の頃、勤務先の近くに小僧寿しの店があった。お昼の休み時間に度々行くので、店員さんとも顔馴染みになった。
ある日、「子猫いらない?」と言われた。「いらない」「ペルシャが掛かっているよ」との一言で気が変わり「それだったら欲しい」と、貰うことにした。
数日してその店員さんの家に貰いに行った 。玄関に入ると、「ムッ」と猫のオシッコの臭いがした。親猫と一緒に奥から出てきた子猫は、思ったより成長していた。
早速猫用キャリーバッグを借りて、単車の荷台に乗せた。動き出した途端、「ギャオー、ギャオー」と鳴き出し、信号待ちの度に優しく声をかけるが止まない。やっと我が家に着いたが一向に鳴き止まず、その晩も鳴き通し。小四の娘は、子猫が心配で眠られず、学校を休む羽目になってしまった。子猫の方は鳴き疲れたのか、その後は静かに眠ってくれた。
名前を付けるにあたり、子猫の肩甲骨のあたりに五円玉位の大きさで茶色があり、確認するように「ミケ」と名付けた。おおかた白で、背中あたりはグレー色。どう見てもミケ猫に見えない。
成長するにつれて、ペルシャが掛かっているだけに雑種であるが気品あふれて見え、仕草も澄ましている。いつも座す所が決まっている。
ミケは団地の二階で、私達家族と一緒に成猫になった。(猫は八ヶ月くらいで成猫になる)
団地の空き地の芝生が色濃くなった頃、いつの間にか雄の赤猫がやって来て、二階のベランダにいるミケをジィーっと見上げているのを見かけるようになった。
ある日、ミケが夜になっても家に戻らなかった。懐中電灯を片手に、車の一台一台の下を照らし「ミケー、ミケー」と呼び乍ら探したが見つからず、次の日もまた次の日も戻って来ない。家事が一段落して、また娘と探していると、年頃になっていた娘は「彼氏と一緒に居るんじゃない!」と言い出した。その言葉に救われながらも、私は内心気が気でなかった。
ミケが戻って来なくなって、四、五日たった朝、勤めに行くために鏡に向かっていると、猫の鳴き声が聞こえた。
あの鳴き声はミケだ!
私は外に飛び出した。団地の突き出した雨除けの庇に……。
あれはミケじゃない! と一瞬思ったが、ミケだ! 白い胸毛は傷を負い赤むけになり、全体の毛並みは艶もなくやつれているが、確かにミケだ。
やっとの思いで手を伸ばし、救いを求めて鳴いているミケの前足をつかみ引き摺り下ろした。
獣医に診てもらい傷の手当てをしてもらった。「そのうちに毛も生えるし」と言われ安堵して連れ帰った。
喧嘩して手負った傷を二、三日じっと耐えていたのだろう。ミケなりに気をふりしぼって戻って来たのだ。
ある時、私の仕事仲間が遊びに来て、お茶しながら笑い声をあげている間、ミケはいつもの所で皆を見下ろしていた。静かになった頃、ミケは急に自分の前足を嘗めだした。ミケの真向かいに座っていた友人が突然「ギャー」っと声を上げた。それまで身じろぎもせずにその場を見ていたミケを、置物だと思っていたと言って胸を撫でおろした。
ミケは、家族が気ままに可愛がり、触ったりしても嫌がらず従順であった。又、「家族皆の悩みを知っているよ~」というような、そんな顔をしていた。
ミケは十九年、私達家族と共に生きた。老猫に多い肝臓病で、口の周りがただれ、ヨダレが出て食欲もなくしていった。最後に一晩中、テレビの隙間で悲しそうな呻き声をあげていた。どうしてやることも出来ずに辛かった。
朝になり最後に振り絞るように「ニャーン」と一声上げた。高い声であったが、サヨナラの声に聞こえた。
まもなく家族が目を離した時、息絶えた。 四月の寒い朝であった。
橋本カントリークラブの近くに「英国風ガーデン動物霊園 アニマルレストガーデン」があるのを娘が調べて、ミケの亡骸をそこへ車で運んだ。
娘は、自分のお気に入りのひざ掛けに包んだミケを、そっと膝に抱き助手席に座った。私は死んだものは触れない。感触が怖いのだ。
「ブー」火葬終了の音がした。係の人が扉を開けると、金網の真ん中にミケのお骨が、寝ている格好そのままの形で出てきた。
「うわーっ――」全身が泣き声に震えた。
なだらかな斜面に広々と色とりどりの花が植えてあり、小さな墓がいっぱい並び、形もいろいろだ。
費用は娘が負担した。帰宅して主人に話すと、「それ位してやってもいいんじゃないか」と言った。私はしんみりとした口調の中に、主人のミケへの深い愛情を感じてうれしかった。
娘はミケにとって母猫代わりの存在のようだった。いや逆に、娘の方がミケに癒され、辛い日々をやり過ごせたのだ。
ミケが亡くなって半年も過ぎた頃、猫が恋しくなりペットショップに見に行ったりしていた。そんなある日、ポストに「パド」という冊子が入っていた。「上げます」「貰って下さい」の欄に、「生後一ヶ月の子猫貰ってください」とあった。どうかなと思いながら電話してみた。
「ブチの子猫です」と、Kと名乗った女性が答えた。「えっブチですか」と、私。
「はいブチなんですが、とても愛嬌のある子なんです。何なら今からでも見てもらいます。家はどの辺りですか」
「河内長野の○○○○です」と、私は自宅の住所を伝えた。
その会話からしばらくしてKさんの赤い外車が家の前で停まった。
籐製のキャリーバックを開けると、ブチの子猫がピョンと出てきた。中にはもう一匹、大きな銀色の猫がくつろいでいた。子猫はそこにあったスリッパで遊び始めた。もう我家のようである。物怖じもせず、可愛い黒い尻尾を立ててウロウロしている様子に、「ブチなんか」と云うこだわりも失せて気に入り、私はすぐに「貰います」と言っていた。
Kさんは貰っていただくには条件があります。それは家に人が居ることです、と先ほどの電話で話していた。勿論私が居るから大丈夫。Kさんは下見に来て安心した様子で、引き渡す日を約束すると子猫を連れて帰っていった。
その日のことを夫に話すと、猫嫌いの夫は「いつ来るんや」と言った。私は、あれっ! 待ってるんかと思い、すぐに電話をして引き取る日を早めてもらった。
こうして我が家に二代目の猫が来た。
初めて来た時と同じキャリーの中に銀色の大きな猫と一緒だった。Kさんは、子猫の一ヶ月間の成長記録の写真とミルク瓶も添えて呉れた。写真を見ると、子猫の成長ぶりと、Kさん宅では前から大型猫を二匹飼っていることが分かった。その銀色猫がブチ子猫の親代わりをしておっぱいを吸わせている。トイレの躾をしている写真も残っていた。
Kさんは帰り際に、この子は生後間もなく庭の片隅で、透明のビニール袋に入れられ、「ミャーミャー」と鳴いていた。この家なら安心と捨て猫の主が思ったのだろうと言った。
娘が一晩考え早速「ノンノ」と名付けたが、家族はいつの間にか「ノン」と呼ぶようになっていた。本で調べると、雑種ではあるが、ノルウェーの森が原産地であるらしい。成長するにつれだんだん長毛になり、毛づくろいする様子は人が餅を食べる様に似て、顎を上の方に延ばしている。ノンは何度も小鳥を銜えて家族に見せに帰ってくる。「ギャー」と家の者が声を上げると、ノンの方がその声に驚き口元が緩むのか、そのすきに小鳥が家中をバタバタと逃げ回り大騒ぎ。ノンも捕り返そうと必死だ。
そんなある日、庭の梅の木をジィーと身じろぎもせず見ているノン。目線の先を追えば、蛇が枝を伝っている。どうしよう! しばらくすると通りがかった人達が「生きてる?」と言い乍ら遠巻きにして見ている。急いで下へ降りてみると、なんと先ほどの蛇がくねくねと地面に降りてきている。それに向かってノンが猫パンチを繰り返している。
お隣へ行き、猫好きのご主人に必死で助けを求めた。毒のない蛇だから大丈夫だと言って、自宅から持ってきた長い棒で何回か突き乍ら袋に閉じ込め、近くの雑木林に放して来てくれて、やっと安心した。
そんなこんなしながら、ノンも十三年目の夏を迎えた。
近頃の夏の異常気象で、人間も熱中症に罹る人が増えてきている最中、ノンも夏毛になっているが、毎日ブラシをかけて梳いてやっても追い付かない。
朝食べた餌を昼には戻し、腹を上にして寝ている。クーラーを掛けても締め切った部屋が苦手なのかすぐ出て行ってしまう。
これでは持たないと獣医に診てもらうと、猫の成人病と診断し、新しく入れた機械でデーターを出してくれた。私は夏バテと思っていたが、本当は植物中毒と後で判明した。
八月二十三日未明に痙攣を起こした。身体を冷やしてやろうと、玄関の涼しいタイルに寝かせると犬歯をむきだして、それがタイルに当たり「コツコツ」と音を立てている。声をかけても反応する余裕がない。朝六時を過ぎたので獣医に連絡した。命の保証はできないが急いで来るようにと言われ、娘と二人で、痙攣し続けるノンを車に乗せ病院へ走った。獣医は様子を見て「八時頃また来てください」と言った。
その場を離れる時、ノンが私をジィーッと見たと娘が言った。八時に行くと、ノンは青い色に星形の模様の棺に静かに収まっていた。獣医はお悔やみを言い、最後に棺は私のプレゼントですと言った。
美しい青色が悲しみを増幅させる。
支払いを済ませ、黙ってノンの棺を受け取り帰宅。
午後には斎場へ。時間通りに終わった後、娘と二人で周辺の山々や雲を見ていると、雲がノンの姿になって浮かんでいる。わけもなく二人は慟哭。「ウワーウワー」と泣き声が木霊した……。十分も経っただろうか、頭が痛くなってきた。
「もう帰ろうか!」「うん」。二人は背後の雲に心を残しながら、静かに車を走らせてその場を離れた。